第3回 「尊徳塾」 ~幼稚園・保育園 若手経営者勉強会~

「株式会社登龍館」が主催している・・・
日本人の勤勉さのモデルとして知られる「二宮尊徳翁」の”至誠”の精神を模範として
20代~40代までの幼稚園・保育園の若手経営者が教育と経営を共に学ぶ勉強会!!
「尊徳塾」
の第3回目が9月13日の金曜日に開催されました。
以前にもお伝えしたように教育面における専任講師は「野口芳宏先生」
そして、私が経営面・運営面の講師&コーディネーターとして関わっております。
幼稚園・保育園・認定こども園の運営者、後継者、現場の職員といった
各種の運営スタイル&ポジションの方々が参加されているので、それぞれの思いや感覚
が凝り固まっていない良い学びの場がそこにはあります!!
今回の野口先生の講義では・・・
「教育者・保育者・実践者としての価値判断基準」
についてお話がありました。
1.人生は判断の連続である
・判断とは・・・「その人の品性や人柄を反映するものである」
・本当の教育のあり方とは?
⇒『自分の責任で判断できる人間を育てることにある』
しかし・・・現代の”学校”は、とかくいろいろなことを禁止したがる(責任を追及されたくないから)
⇒それが、
親や家庭が責任を持って考える場や環境を奪っているのである!!
・現代の人達や教育現場を見ていて感じることは・・・『判断の迎合傾向』
⇒世の中の大多数がそうだから・・・、自分で真剣に考えず、
その他多数の人間に判断を委ねている、合わせている傾向があるのではないか。
・自己責任に基づく判断を子ども達や親ができる環境を設定することが大切
⇒最終的に責任ある判断は学校ではなく、家庭にあるべきである!!
【判断をするときのポイント】
①本質的には何が一番大切か、教育のねらいはどこにあるのかを考えること
②何が望ましい判断かをしっかり留まって考えること
③目先の損得で判断をすると、最終的には間違うことになる
④伝統やそこに根付いているものを簡単に変えてはならない、軽んじてはならない
・リーダーがする判断は、『独断専行』でよいが、そこに『大義名分』がなければならない
⇒最終的に責任をとる覚悟に基づいた、慎重な判断が求められる
⇒自分の判断が及ぼす『結果と影響』について、
いろいろなことを事前に深く推察することができる人間はリーダー適正がある
2.判断基準について
・判断するときのあり方・・・どちらを選択するか??
EX) ①苦しいか楽か(めんどうか簡単か)②損か得か③複雑か単純か・・・
『楽・得・単』を選択する人間 ⇒ 小人と呼ばれる ⇒ 『知識人』
『苦・損・複』を選択する人間 ⇒ 君子と呼ばれる ⇒ 『教養人』
あなたはただの知識人のままでいいのか・・・教育者は教養人でなければならない!!
・【教養】 = 【知識】 + 【徳】
⇒知識人から教養人に進化するためには、『徳』とは何かを学び身につけなければならない!!
『賢人から学ぶ愚者は少なく、
愚者から学ぶ賢人は多い』(ゲーテ)
常識的に言えば、当然愚かな者は賢い者から学ぶはずだが、実際はそうではない。
愚者とは賢人からさえも学ばない者である。そして賢い者は常に学び続けるので、
愚者からさえも様々のことを学ぶことができるのである。
わかりやすくお話いただく野口先生の講義は、同じ講師をさせていただいている自分が
恥ずかしくなるくらい奥深いものです。
自分はまだまだ浅い人間だなと実感させられます
自分も年月を経て、このような深みのある話ができるようになりたいな~と
思いながら今回もお聞きしていました。
そして、あらためて人間として、経営者としての判断基準や
CLPのこれからの事業展開に対して何を大切にするべきかを整理する時間にもなりました。
少なくとも、目先の損得に目が眩まないように自分を更に戒めたいと思います!!
そして今回の自分の講義内容は・・・ 簡単に目次だけ整理しておきます。
1.園児募集戦略の基本フレーム
(1)「園児募集活動の正しい理解」 ~目的ではなく自園成長のプロセスである~
(2)「ターゲティングの重要性」 ~2つのターゲットを検討する~
①顧客②エリア
※募集強化エリアの見極め方とポイント(エリアポテンシャルマトリックス)
※シェアは人気のバロメーター(ランチェスターの法則の概要理解)
2.園児募集ストーリーの組み立て方
~欲しい情報、欲しい体験、欲しい魅力を適切なタイミングで~
過去を分析して未来を予想する = PDCAサイクルの理解と実践
(1)「募集数値シミュレーション」 ~目標設定は具体的に~
①新入園児②弟妹人数
(2)「入園アプローチ分析」 ~効果的な入園パターンを見つけよう~
※未就園児名簿管理の仕組み構築の重要性
※(ルール化①)
名簿管理を疎かにしている組織は、どこも業績を上げることができていない
(3)「年間の募集シナリオづくり」 ~保護者の心理状態を考えたメッセージの伝え方~
【ポイント①】
①どの時期に
②どのような情報が欲しくて
③どのような体験を望んでいて
④その園のどんな魅力を欲しているか
⇒最終的に・・・
「どうしてもこの園に自分の子どもを入園させたい!」という心理に導くストーリーの作成
【ポイント②】
認知度アップから共感度アップへのシフトチェンジ ~年間を2つのフェーズで考える~
(1月~6月)=『認知度アップ』(自園を正しく知ってもらうフェーズ)
(7月~12月)=『共感度アップ』(園の思い・考え・取り組みに共感してもらうフェーズ)
⇒上記を通じて、
『自園のファンを創ること』 それが、園児募集活動である!!
(4)「入園説明会は思いの伝達の集大成
3.自園の伝達力アップ ~自園の魅力が伝わるプロモーション活動とツール作成~
【プロモーションツールを作成する上で準備・整理すること】
① 目的は何か・・・見た人がどんな気持ちになって、どんな行動をしてほしいのか
② ターゲットの設定・・・誰を対象にしているのか
③ 自園の独自固有の長所は何か・・・他園にはない自園の魅力は何か
④ ターゲットに一番伝えたいメッセージは何か・・・プロダクトアウトの視点
⑤ ターゲットが知りたい情報内容は何か・・・マーケットインの視点
まあ、長くなってしまいましたが、こうやってブログに掲載してみると
かなり、内容の濃い勉強会だなと思いますね!!
そして、昨日の『ディスカッションタイム』では、各園からの持ち寄った、
入園説明会で活用する、映像作品をシェアする時間となりました~。。。
各園ともに素晴らしい完成度のものでしたね。
私が、各作品を見て、その場で少しだけ整理させてもらったことは・・・
①動画と静止画の使い分け
※思いやイメージを伝えるのは、そのシーンが凝縮されている画像とメッセージで!!
※一連の動きや活動内容は、動画を編集してショートカットバージョンで解説を!!
活動内容については、ただ見せるだけでは、プロと素人による解釈のズレが生じるので
見るべき視点とその意義を解説して、全体共有することが大切。
②残念ながら長編や超大作は、かけた時間やコストほど、保護者へのインパクトがない
※忙しい世の中で1時間もかけて、園の紹介DVDを見てくれる保護者はそんなに多くない
※ホームページに自園紹介映像などを掲載するならば本当にテレビCMのイメージで
※入園説明会内で見てもらう映像作品は、5分程度にまとめること!!
③プロモーションツールですべて園の内容を伝えようとしないこと(それは自己満足に過ぎない)
※あくまでも、園に興味を持って、見学したいなとか、イベント参加してみようと
感じてもらうまでの仕掛け(フック)として機能させること
※教育施設は、パンフレットやホームページですべてを伝えようとしてはいけない
あくまで教育現場に来て、何かを感じとってもらうことに重きをおくべきである
といったことをお伝えしました~(^◇^)
当然ながら、勉強会後の懇親会も盛り上がっていましたね!!
同じ学びの内容であっても、共有する仲間によって、その捉え方や活かし方は
大きく変わっていきます。
『何を学ぶかも大切ですが、何を誰と学ぶがもっと大切!!』
そう思える勉強会に講師として
関われていることに感謝して、次回も頑張りたいと思います!!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
そして、誰から学ぶかも大切ですよね。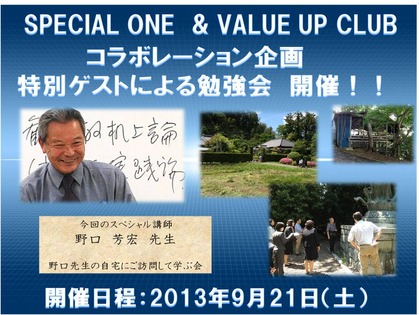
現在、静岡県や青森県からも参加申込いただいております。
まだ空きがありますので、お申込み・お問い合わせお待ちしております!!(残席4席)
詳細はこちらをクリック
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
